since 2021
Welcome to our site
奥羽観跡聞老志
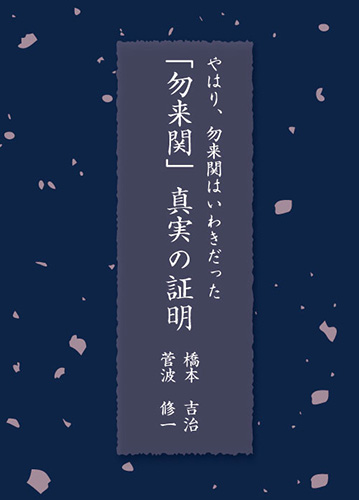
奥羽観跡聞老志
この書に、なこその関を詠った平安の和歌がいくつも紹介されている。その全ての歌が、いわきの奈古曽の関を詠ったものとして記されている。

伊達(仙台)藩主の命で作られたのがこの著である。 奈古曾関は、この著の「菊田郡」の中で、実に詳細に紙数を使って説明されている。本著は 一次史料である。

「立別れ二十日あまりになりけり けふ(今日)やなこその関をこゆらん」
平安末期の1104年頃、源師頼が詠んだ和歌で「堀川院百首」に収められている。
都から「なこその関」までの距離を一般人の平均歩測で割ると符合している。

「九面や 浪打ちよせて道もなし ここをなこそのせきといふらん」
この歌の作者が西行法師になっていますが、西行の歌にはないようです。
似た歌で飛鳥井雅宣の歌があります。
「九面や潮満ちくれば道もなし ここをなこそのせきといふらん」
江戸時代になったばかりの1609年頃のものですが、当地方では有名な歌です。この歌と混同したように思えます。九面にあった関は、切通しの関のことで江戸時代初頭にできた新道です。西行の時代は旧道(ほぼ現在地)にあったと思われます。

