since 2021
Welcome to our site
1.「なこその関」 いわき所在の蓋然性
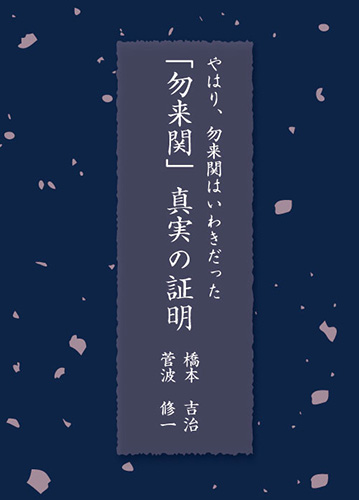
副題 飛鳥井家「家集」 に見る 「なこその関」1) の連続性について 2024,2,24 勿来関研究会 文責 橋本清流
- 「なこその関」いわき所在の概括
江戸時代半ばから末期に至る 「なこその関」のいわき所在を示す文献史料は、数十点以上に及ぶ。では江戸時代初頭以前はというと、限られてくる。まず、最近私共が紹介した『太平記大全』 (1659年) を挙げる事ができる。そこに「名古曽ノ関打チ越ヘテ岩城ノ郡二至ル」とあるからである。三万の軍騎が常陸国から岩城郡を経て一時期府を置いた伊達の霊山に向かったというのである。軍記なので一次史料ではないが、連載物で広く読まれていた冊子である。地理的記述は信ずることができる。手元にあるのは五代将軍綱吉が所持していたものなので、将軍学の教材としも使われていたのである。この記述から名古曽の関が常陸国と岩城郡との間にあって、軍馬が打ち越えて行ける程度の小高い山の上にあることがわかる。北茨城の富士ヶ丘といわき側の出蔵・酒井街道の国境を彷彿させる表現である。
「なこその関」 いわき所在を示す次の史料として 『太平記大全』 のおよそ五十年前に、本論の主人公になる飛鳥井雅宣が1609年頃に実地で詠った歌がある。「ここつらや しおみちくれば みちもなし ここをな こそのせきといふらむ」 (東遊雑記) である。この歌には 「九面(ここづら)」 と 「なこその関」 という二つの名称が出てくる。場所を特定できる名称が一詩に二つある歌は少ない。このような歌を歌人が詠むだろうかという疑問があるためか、いわきの地域史家は、歴史を語る資料にしていない。したがってもし、この歌の 真実性を説明できるなら、先の 『太平記大全』 を数十年遡って 「なこその関」 いわき所在を立証できるのである。
次に平安時代の史料について述べる。『月詣和歌集』にある源義家の歌の詞書に「みちのくに くたりまいりけるときなこその関にてよめる」 (1182年) とある。また 『千載和歌集』 の同歌の詞書に「陸奥国にまかりける時なこその関にて花のちりければよめる」 (1188年) とある。
そして『後拾遺和歌集』 の能因の歌の詞書には 「みちのくにまかり下りけるに白川の関にてよみ侍りける」 とある。これらを比較すると 「なこその関」 が白河関同様、都からきて陸奥の国に入ってすぐのところにあったことになる。
また『堀川院百首』 にある 1104年頃の源師頼の 「立別 廿日あまりに成りにけり けふや 名社の関や越らん」 2) によって、都から名古曽の関までの距離を平均歩速(約32キロ/日)で除すと二十一日ほどにな る。歌と合致することがわかる。これらによって名古曽の関が、東は海岸の九面から西は出蔵の山まで東西数キロ 3) の範囲を出るものではないことがわかるのである。
このように「なこその関」 いわき所在を示す史料を概括するとわかることがある。江戸時代と平安時代の史料はあるものの、その間の鎌倉時代から室町、安土桃山時代に至るおよそ四百年間の史料がなかったのである。本稿の目的は、そこを埋めることである。
2. 飛鳥井家の「なこその関」 の歌
飛鳥井家は、鎌倉時代前期に飛鳥井雅経を祖として誕生した。父親難波頼経の家業としての蹴鞠を受け継 ぐとともに歌道に秀でていたため初代雅経は後鳥羽上皇に用いられた。1205年には、『新古今和歌集』の撰 者を命じられるほどだった。飛鳥井家系譜の中で、鎌倉時代後期頃から江戸時代初頭にかけて「なこその関」を和歌に詠った人物が四人いる。共に歌道家の飛鳥井本家を継いでいる人物なので、彼らが先祖の歌を知っていたことは当然である。そこで私は、この四人が歌った「なこその関」 は同じものであろうとの推測をしたのである。それが成り立てば名古曽の関がいわきに所在していたことになり、その確実性が江戸時代初頭より鎌倉時代半ばまで約三百年遡ることになるのである。
飛鳥井家の四人の歌を順を追ってみてみたい。まず初めに飛鳥井家第三代当主の雅有は、三首詠っている。
① 【 しひてゆく こころよいかに あつまちの なこそのせきの なをはきかすや 】 (隣女集) 私釈 どのようにすれば、東路の名古曽の関の名を聞かせて、この恋を諦めさせられるだろうか。
② 【 あふさかに あらぬなこその せきもりを わかこいちには たれかすゑけむ】 (隣女集) 私釈 逢坂の関にいないはずの名古曽の関守を我が恋路に誰がおいたのか。
③ なもつらし わかみひとつのためなれや ひともなこその せきのとさしは】 (雅有集) 私釈 自分のせいで、名古曽の関のように、この恋が閉ざされたのはつらいことだ。
この隣女集も雅有集も、飛鳥井家の歌をまとめたいわゆる「家集」であり、自分の歌だけでなく、先祖の歌も撰している。これらの歌集が飛鳥井家で作られ、師範書(家学) として使われていたことは論をまたない。この歌の制作年はわからないが、雅有の生没は1241年から1301年なので鎌倉時代半ばから後期になる。 次が飛鳥井家第七代当主雅世の和歌である。
④ 【わかかたに なこそのせきは なきものを いつあつまちに とほさかりけむ】(雅世集) 私釈 私の方には名古曽の関のように拒絶するようなものはなかったと思うのだが、どうして・・・
これも「雅世集」 と言われる飛鳥井家の 「家集」である。雅世の生没は1390年から1452年なので室町時代 前期の歌である。その子の八代当主雅親が詠んだ歌が次のものである。
⑤ 【 こころたに せめてかよはは あつまちの なこそのせきは よしへたつとも】 (続亜槐集) 私釈 たとえ私たちの間に東路の名古曽の関があっても、心さえ通じていれば・・・
この続亜槐集も、飛鳥井家の「家集」 であり「家学」 として後代に伝えるために残したものである。 雅親の生没は1417年から1491年なので室町中期の歌と考えられる。
これらの歌を整理してみる。

①から⑤までは鎌倉時代後期から室町時代半ばまでのおよそ二百年間ほどの歌になる。「なこその関」が一貫して「恐ろしく・難き関」として詠まれているが、このころ関は廃止されていた。歌枕としてのみ使われていたのである。またこの三人は現地には来ていない。
3. 飛鳥井雅宣の 「なこその関」の歌
飛鳥井家で「なこその関」 を歌った四人目が本論の主人公の十四代当主雅宣である。難波宗勝とも飛鳥井雅胤ともいう。

私釈 潮が満ちてくると道もなくなるような九面4) だが、ここがあの名古曽の関というのか。
この歌を詠んだ雅宣の生没は、1586年から1651年である。1609年に事件を起こし、現いわき市遠野町に三年ほど流されていた。5) この歌はその時のものである。
その歌が載っている 『東遊雑記』 を書いた古川古松軒は、長久保赤水と歳の離れた盟友である。江戸彰考館 6) で仮借されたと考えられる 「勿来関」7) も使っている。彼は東北地方の旅から江戸への帰路、泉から植田ま で来て、数キロ南にある勿来の関に来なかった。植田から西に折れて御斉所街道を中通りに向かったのであ る。文中に「勿来」 の文字を使ったり、赤水作の勿来の関の漢詩などを紹介している。ちなみに『東遊雑記』刊行が1788年で赤水の 『東奥紀行』刊行が1792年である。古川古松軒は赤水の漢詩を本人より四年前に発表してしまっていたことになる。しかも『東遊雑記』の漢詩には作者の名前がない。二人の間柄を示すユニークな出来事である。 8) 飛鳥井雅宣の九面の歌が 『東遊雑記』に紹介されている理由を知るために、もう一度赤水の 『東奥紀行』を見てみる。すると頭注に次のようにあった。

『東遊雑記』は 「ここを」 で 『東奥紀行』 が 「これを」 になっているほかは同じである。現在地元いわき市の関跡近辺や上遠野町の「住居跡」の歌碑は 『東遊雑記』を用いている。「勿来関」 に来ていない古川古松軒が地元にしか残っていない雅宣の歌を記している。それは、彼が江戸彰考館に出入りしていたからわかっていたのである。
それは『東奥紀行』には、数十年前の旅の下書き (2022年に国の重要文化財になった)があるのでわかる。九面の歌は、海のすぐそばを画いているので、切通 (斫通)の関を歌ったものである。ここは、幾度かの変遷を経て江戸時代当初に隧道から切通になった新道である。旧道はここから西におよそ870メートルほどの山中にあると『奥羽観蹟聞老志』 や 『新編常陸国誌』 は伝えている。現在の関跡地付近になる。
九面の歌の結びが 「なこそのせきといふらん」と単純な推量になっている。したがって名のある名古曽の 関とは、潮が満ちてくると路が無くなるような所だったのかということになる。
また「いふらん」 は、名古曽の関が陸奥国の入口にあることを事前に知っていたことを示している。かつて「なこその関」 が 「恐ろしく・難き関」 と歌われていたことを知っていたのである。
飛鳥井家に伝わる 「家集」 としての 「家学」 の重みを知れば、そのことは疑う余地のないことである。その関跡に来てみて、想像していたイメージと違うので「いふらん」と結んだのである。
- 「なこその関」 いわき所在の蓋然性
飛鳥井雅宣は、実際に現いわき市勿来町九面に来て、名古曽の関地を見聞したのである。したがって鎌倉時代中半から室町時代にかけて祖先が詠んだ 「なこその関」 と彼が歌った 「なこその関」 は、同一のものであるとの結論にいたった。
飛鳥井家累代の歌によって、「なこその関」 いわき所在が江戸時代初頭より鎌倉時代半ばまで、遡れることが明らかになったのである。
註
1) 本項では、和歌には 「なこその関」、江戸中期以前は 「名古曽の関」、その後は 「勿来関」を用いた。
2) 江戸期写本による。ふりがなは著者。
3) 南北は、現酒井と大高の郡役所跡を含む三キロの範囲を推定。
4) 九面は現在「ここづら」と発音されている。九浦がなまったものを漢字表記したともの考えられる。
5) 飛鳥井雅宣については、流島地を伊豆とする説もある。いわきの渡辺家(近年まであったが今は絶)に伝 えられていた話しもある。いわき市遠野小学校の一隅に、居住地跡として碑が建てられてある。 また同小学校校歌には 「あすかい」 の名が歌われている。
6) 水戸黄門が設けた『大日本史』 編纂のための修史局。江戸と水戸にあった。
7) 「勿来関」の初見は、(1707年)刊の森尚謙の 『優儼塾先生文集』になる。その次が1778年、長久保赤水の 「平潟洞門碑」になる。共に「勿来の関」 いわき所在を示すものである。又、二人は年代は違うが江戸彰考館の同門になる。
8) 『長久保赤水の交遊』 長久保片雲着 参照

2.「菊多の関」が「なこその関」であることの立証
副題 征夷終結で関は不要になったが菊多の関は残されていた。小野小町はそれを「なこその関」と歌った。
1. はじめに
「勿来関」の所在については、いわき市の最南端で北茨城市との県境近くにあることで知られていた。駅名や地名にもなっており、跡地には碑などもありそれを疑うものはいなかったのだが2000年前後あたりから宮城県利府町が本当の場所なのだとの論調が登場するようになってきた。はじめの頃は気にもしなかったのだが、地元新聞に大々的に出たり、チラシにして配られたり地元歴史団体の機関誌に載ったりして、興味を持って読むようになった。勿来の文字を使って生活をしている者としては当然のことだろう。
福島県の教育文化関係のトップを歴任した方や地元マスコミ関係者、公共関係機関の方々も名を連ねていて、多賀城や利府の関跡バスツアー、利府町での講演会まで行われていたのである。
それから二十年以上経って、いわき市関係者の中に利府説が深く浸透していることを佐藤一先生の『勿来関と源義家』復刻本作成の中で否応なしに知ることになったのである。
しかし利府説に疑問を持った地元の有志数名で勿来関研究会を発足し、利府説関係文献を始め勿来の関に関する古書籍等を収集し読み合わせや討議を重ねた。その結果、いつくつもの新発見によって「なこその関」がいわき市所在であることを確信したのである。(詳細は当ホームページ「勿来関Q&A」などをご覧いただきたい)
とにかくこれだけの歴史的遺産が当地にありながら正式な発掘調査が一度もされなかったのである。かたや奥州三古関といわれる白河の関や鼠ヶ関は発掘調査もされそれぞれ指定史跡になっているのである。白河の関と共に『弘仁格抄』に出てくる菊多の関は菊多(田)の地名を持つ当地以外にはない。しかしそれが後に和歌に詠まれた「なこその関」であることが明確に立証できないばかりに気が付いてみれば他所に持っていかれようとしていたのである。本小論は短編ではあるが「菊多の関」が「なこその関」であることを立証するものであり、さらなる勿来の関の研究の基礎としてまた地域文化社会活性化への大いなる船出として活用できるものと自負している。
2. 陸奥国の征夷は終了し、関は不要になった
774年,後に38年戦争などと言われる陸奥の国への派遣が開始された。その後802年には多賀城にあった鎮守府が約120kmほど北の胆沢城に移された。蝦夷との前線が北移したことを示すものである。この時点で多賀城周辺にあった首府防衛の総(左右)の関などは不要になったと思われる。
すなわちこの時点で多賀城周辺には暴れる蝦夷はいなかったのである。いわゆる蝦夷との境ではなかったのである。805年に陸奥の国の(東)海道にあった伝馬が廃止されたことからも、蝦夷との戦いが終息へ近づいていたことがわかるのである。
811(812)年、ついに38年間に及ぶ征夷の終結が宣言された。このことは遅くとも812年には津軽と羽州の一部を除いて陸奥の国のほぼ全関が不要になったことを示している。
3. 菊多の関は機能していた
陸奥の国の征夷が終結し関が不要になったのに、850年頃小野小町によって始めて「なこその関もすえなくに」と、すなわち「二人の間になこその関を置いたことなどなかったのに」とまるで二人を遮断する活きている関の代名詞として歌われたのである。このことの出所になったと考えられる事件が歌の2年前にあった。848年に起きた鹿島神宮宮司通行拒否事件である。陸奥の分社に向かおうとした宮司が関守に「前例がない」(類聚三代格)とのことで通行を拒否されたのである。官位ある神社の宮司が関の通行を拒否されたユニークなニュースは朝廷への訴えによって瞬く間に都に広まったと思われる。征夷も終わり関も不要になっていたと思っていたのに、陸奥の入口の関はそんなに厳しかったのだ。これは歌に使えると考えられたのだろう。
この厳しい関の取締りが何故起きたのかの根拠として、835年の勅(類聚三代格)がある。陸奥の国の入口の白河と菊多の関のみ通行を厳しくするようにとの通達があったのである。この宮司通行止めの訴えが許可されたのは18年も過ぎた866年である。(類聚三代格・三代実録)
ともかく陸奥の国の関が不要になっていたのに菊多の関が機能していたことがわかる何よりの歴史的ユニークな事件である。
4. 「なこその関」の誕生と消滅
宮司通行拒否事件の2年後の850年頃、小野小町が「みるめかる あまのゆききのみなとじに なこその関も わがすえなくに」と初めて「なこその関」を詠んだのである。
私訳 海女が港路を自由に行き来するように 二人の間に「なこその関」を置いたことはなかったのだが
「なこその関」が二人を遮断する関として初めて歌われたのである。850年頃この関は陸奥の国で活きていたのである。
すなわち小野小町の「なこその関」は、陸奥の国の玄関で関の機能を果たしていた菊多の関以外にないのである。菊多の関を詠った和歌は一首もない。このことからも都で菊多の名称は知られていなかったとみられるのである。「なこそ」とは百人一首にある公任の「名こそ流れて」と同じく「名前は流れたが」あるいは「名こそわからないが」程度の言葉を縮めて「なこそ」と歌にして理解しあえたのではないだろうか。それが小野小町の歌によって広まったと考えるのが妥当である。
繰り返しになるが、小野小町が「なこその関」と歌った850年頃、陸奥の国に関は不要だったのだから「蝦夷よ来る勿れ」と解釈するのは間違いである。また歌の内容から機能している関を歌っている。以上のことから陸奥の入口で機能していた関を「なこその関」と歌ったのであり、「菊多の関」が「なこその関」だったのである。
私論1. 「なこその関」の呼称について
「なこそ」とは地元の地名でも地元で発生した言葉でもない。では都人が歌にした「なこそ」とは、どんな意味だったのだろうか。江戸時代には「浪越」や「蝦夷よ来る勿れ」の意味だろうとか、近年では「な・・・そ」は禁止の意味の両面接辞にカ行変格活用の未然形の来(こ)が挟まれた「な来そ」に由来するなどとなかなか難しいことが言われている。
勿来関研究会の調査で、現在使われている「勿来」の文字は1707年頃に水戸藩によって仮借・一作されたものであることがわかっている。したがって「来る勿れ」との言い方もその後にできた熟語である。文法がどうのというのも「勿来」の文字から解釈したものなので、「なこそ」本来の意味にはならない。「浪越」は江戸時代に海側の九面(ここづら)に新道としての隧道(現切通)が作られてからのことで歌や文献によれば元々は山の上に関があったといわれていることから、これもあてはまらない。和歌の内容からしても都人からするなら「行く勿れ」というべきであり、「来る勿れ」は地元からの立場なのでその名が地元に残っていたはずである。しかし、鎌倉室町期時代に地元に「なこそ」の名称が残っていた証拠はなにもない。地元で「なこそ」が見えてきたのは江戸時代半ばの長久保赤水撰の平潟洞門の碑や『東奥紀行』あたりからである。
日文研データーベースで「なこそ」を検索すると441首出てくる。この中から「はな(花)こそ」の150首、「なこそのせき」の60首、「せきのなこそ」の4首、「なこそのやま」の2首を除いた223首(重複している歌もあるのでおおよそになる)を見てみるとほとんどの「なこそ」が「名(前)こそ」の意味に集約されるのである。京都の大沢の池の片隅に百人一首に出てくる「名古曽滝」がある。京都の文化財担当の方に尋ねると藤原公任の「たきのねは たえてひさしく なりぬれと なこそなかれて なほきこえけれ」から名付けられたようですとのことだった。「名こそ流れて」から都人によって「名古曽」と名付けられていたのである。「名こそ流れて」すなわち「本当の名こそわからないが」程度のことを縮めて「なこそ」と言ったものと考えられるのである。
清少納言の『枕草子』にでてくる関の名前を見てみるとそのことが類推できる。「(相)逢坂の関、須磨の関、志ら川の関、衣の関、くきたの関、はばかりの関、ただこえの関、清見の関、見る目の関、よしなよしなの関、なこその関」写本によって若干の違いはあるがこれらの関名の中で文法から編み出されたようなものは見当たらない。もっと単純に遊び心で付けられたような関名が多い。「なこその関」も同様と見られる。よって、「なこその関」が六国史等公文書にないのは当然である。それをもって「なこその関」そのものの存在を否定するのは大きな間違いである。
私論2. 「なこその関」の変遷
源義家の「ふくかせを なこそのせきと おもへとも みちもせにちる やまさくらかな」が載っている歌集は、1182年の『月詣和歌集』と1188年の『千載和歌集』である。ここには詞書(ことばがき)があってそれぞれ「みちのくへ くたりまいりけるとき なこそのせきにてよめる」と「陸奥国にまかりけるとき なこその関にて 花のちりけれはよめる」とある。これを『後拾遺和歌集』に収められた能因の白河の関の歌の詞書の「みちのくに まかり下けるに 白川の関にて 読み侍りける」と見比べると「なこその関」も白河の関と同様陸奥の玄関口にあることがわかる。すなわち「菊多の関イコールなこその関」の図式がこのことからも成り立つのである。
「吹く風を 名古曽の関と おもへども」からすると、この歌は実地で歌ったものではない。陸奥の戦いを私戦とされた無念の心を都で吹く風に託して歌ったものである。この歌の制作年はわからないが彼の生没が1039年から1106年頃とされているので亡くなってからでも80年近く経っていることになる。時の朝廷批判が匂うからではないだろうか。
彼が関わった前九年の役や後三年の役の頃の「なこその関」は機能していたのかについて考えてみたい。明確な史料はない。しかし、源義家の参戦を客観的に見れば、811(812)年すでに征夷は終結していたのだから奥州の豪族同士の権力闘争への介入だったことは間違いない。835年に白河と菊多の関のみ看過が発令され機能していたが義家の頃にはすでに廃止されていたようである。それが次の源信明の歌からもわかる。
「なこそよに なこそのせきは いきかうと ひともととめぬ なのみなりけり」
「私訳」 名古曽の関の名は人の行き来もできない関だと恐れられていたのになのみだけだった
源信明の生没が910年から970年頃だが、この時すでに関は機能していなかったようである。
ところがその頃の歌で関の通行が遮断されているような歌がいくつも出てくる。紀貫之の「おしめとも とまりもあらす ゆくはるを なこそのやまの せきもとめなむ」(夫木抄)がある。山の上にある関がまるで活きているような風景である。紀貫之の生没が866年頃から945年である。 あるいは、藤原道綱の母の『蜻蛉日記』(かげろうにっき)に「こえしのふる あいさかよりも おとにきく なこそのせきは かたきせきとしらなむ」の和歌がある。制作が954年から974年頃になる。歌からは関が機能していたように思われる。これらの歌を史実と見るなら「なこその関」の廃止は955年頃になる。その後に出てくる「なこその関」は遮断の関の代名詞すなわちただ歌枕として使われただけということになる。
したがって源義家の活躍した1083年頃や室町南北朝の戦乱の頃も名のみの関だったのである。『太平記大全』に「名古曽の関打ち越えて岩城郡へ至る」とあるが、これは奥州との国境の代名詞として用いたものでその時「なこその関」は、とっくになかったのである。その後、関が関所として必要になったのは江戸時代になって藩制度ができてからで、自由往来を取り締まるためである。なこその場合は旧道に対する新道として現切通付近に関所が造られたそうである。
江戸時代になって間もなくの1609年頃、飛鳥井雅宣が実地九面で歌ったとされる歌がある。「ここづらや しおみちくればみちもなし ここをなこそのせきといふらん」この歌は海に近い切通の関の前身の隧道の頃のものと思われる。江戸時代になったばかりであり、この歌からは名古曽の関が関所として機能していた風景は見えない。飛鳥井家累代が歌った「なこその関」のイメージと大きく違って青い大海原を眼前に、遠く小名の三崎まで一望できるこの絶景が大好きになって流罪地の上遠野から何度も九面の渡辺家に来たと伝えられている。「このような所があの冷酷無残な関として恐れられ、歌枕になっている「なこその関」だったのかというのである。この時点では関所はなかったと思われる。関所ができるのは藩政が緒に就くもう少し後のことになると思われる。
5. 最後に
陸奥の国の関が不要だった時期に、菊多の関は関の看過の令によって活きていた。実際そこを通ろうとした宮司が通行を拒否されたのである。その約2年後に小野小町によって初めて「なこその関」が「恋の通行を遮断する活きた関」として登場するのである。この時陸奥の国で活きていた関は白河と菊多の関のみだったのである。白河は現在も同じ呼称なので、必然的に「なこその関」とは菊多(田)の関のことになる。
陸奥の国の征夷が終わり伝馬も兵隊もいないのに、利府の関などを通行遮断の「なこその関」として歌うわけがない。多賀城に近いので理に適っているとの論は全く逆さまであることが明瞭である。 本論のような基本的なことが何故論じられなかったのか不思議でならない。本論は、単純で短いが「なこその関」他所説に対する反論としても決定打であると確信するものである。38年戦争の終結の意味を受け止め、菊多の関の看過と宮司通行拒否事件を受けての小野小町の歌をよくよく眺めれば、「菊多の関」が「なこその関」だったことは明らかである。
最近、いわき市長が各種会合や記者会見で勿来の関への前向きな発言をされている。勿来の関の基本事項の締めくくりとしての本論がやがて必ず役立つものと思う。なお、「勿来の関」について取巻く多くの問題は当勿来関研究会の研究調査によって解決していると思っている。このホームページの各所をご覧いただきたい。皆様の研究に寄与できれば望外である。
文章のいたらない点はお許しいただいてこの項を終える。
白鷺池の玄正庵にて 清流