since 2021
Welcome to our site
8. 源将軍の歌に思う
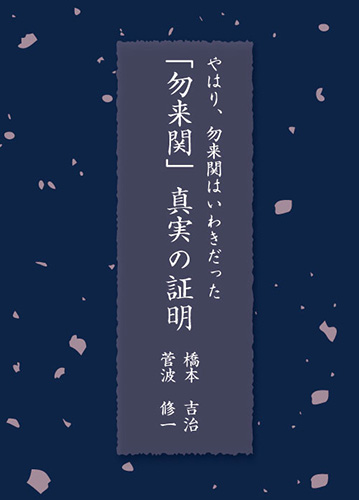
佐藤一先生は、亡くなるまで毎年勿来関跡の老松を描いていた。その二十六枚が手元にある。御家族に頂いたものだが晩年には、虚飾を払って松ノ木だけを画いている。 先生が尊敬した源義家をその木の下に見ていたのだろう。
又、絶筆になった絵は掛け軸になっている桜花の下の八幡将軍の馬上姿だ。百歳の奥様によると文字は奥様の手によるもので、昨年の正月初めて床の間に飾ったという。
先生の著書を見て初めは勿来関を知るのに何故、源義家を大きく紹介しているのかと思ったが段々とわかってきたような気がする。
関山に自家の土地があり、幼い時から関跡で遊んでいた先生の文武両道を旨とする鏡だったのだ。そして晩年の絵は将軍の姿に自分を重ねていたように見える。
先生は著書に次のように残している。
「義家は天下の平和を希(こいねが)って、私恩を以て部下を愛撫し覇業を大成したのである。関の柵戸は廃れ去っても義家の名は山桜と共に久遠の命を得てるのである。義家の徳を讃え句を添えてこの項を終る。
はじめ よむ
関跡の近道寒し山ざくら 朽ちてなほ桜ありけり名古曽関
覇権反対の私にとっては、父に反発する子供のようだが、時代の違いのしからしむところなのだろうか、吹く風の歌についても私の考えがある。
「ふくかせを なこそのせきとおもえともみちもせにちる やまさくらかな」
この歌は、名古曽関で詠ったと詞書にあり、誰もがそのように解説している。しかし、歌の中の吹く風は、どこで吹いた風だったのだろう。名古曽の関で詠んだのなら、「吹く風」はいらなかったと思う。 仮に桜を散らす風が必要だったのなら句の並びが違うと思う。
例えば、「吹く風に みちもせに散る やまさくら 名古曽の関にしはしやすらく」
などでもよかったはずだ。「おもえども」の言葉からしても、現地で詠うなら吹く風に名古曽の関を「思う」必要はなく、見事な落花を讃えるだけでよかったはずだ。この歌は現地で詠ったのではない。 義家と阿部貞任が岩手県の衣川でやり取りした歌は感動ものだが、あれが本当だとして義家ほどの人物が、落桜が見事なだけで詠うだろうか。それに桜の咲く頃関山を歩いたが、あの歌に似合うような風景はないし、山桜の花数は少ないので道が狭くなるほどにはならないと思う。あの歌が歌集に載るまで八十年も要している。超有名人だったのだから、遅すぎる。やはり何かある。
以上のことから、あの歌をよくよく眺めていると、「みちもせにちる」は「道も狭に散る」でなく、「陸奥(みち)も背に散る」の意だったのなら、私戦との屈辱を受けた陸奥の戦いの無念を見事に歌って いると思えたのだ。歌集の選者はそのことを知っていたから、単に「陸奥に下りけるとき名古曽の関で詠んだ」とソフトな表現にしたように思える。
この歌で、名古曽の関の位置を論ずる方ばかりだが、詞書からしても名古曽の関が陸奥の入り口にあることは疑う余地がない。義家のこの歌は、陸奥の戦いの無念さを表したもので、読者がそれとわかるように、陸奥の入り口にある有名な名古曽の関の名を出したものと思われる。散る桜花に自分のおかれた心境を歌にして詠んだのだ。私にはそのように思える。
そのように考えると、良し悪しは別にして、国語と社会科の教師だった一先生が何故義家を愛したのかがわかるような気がする。